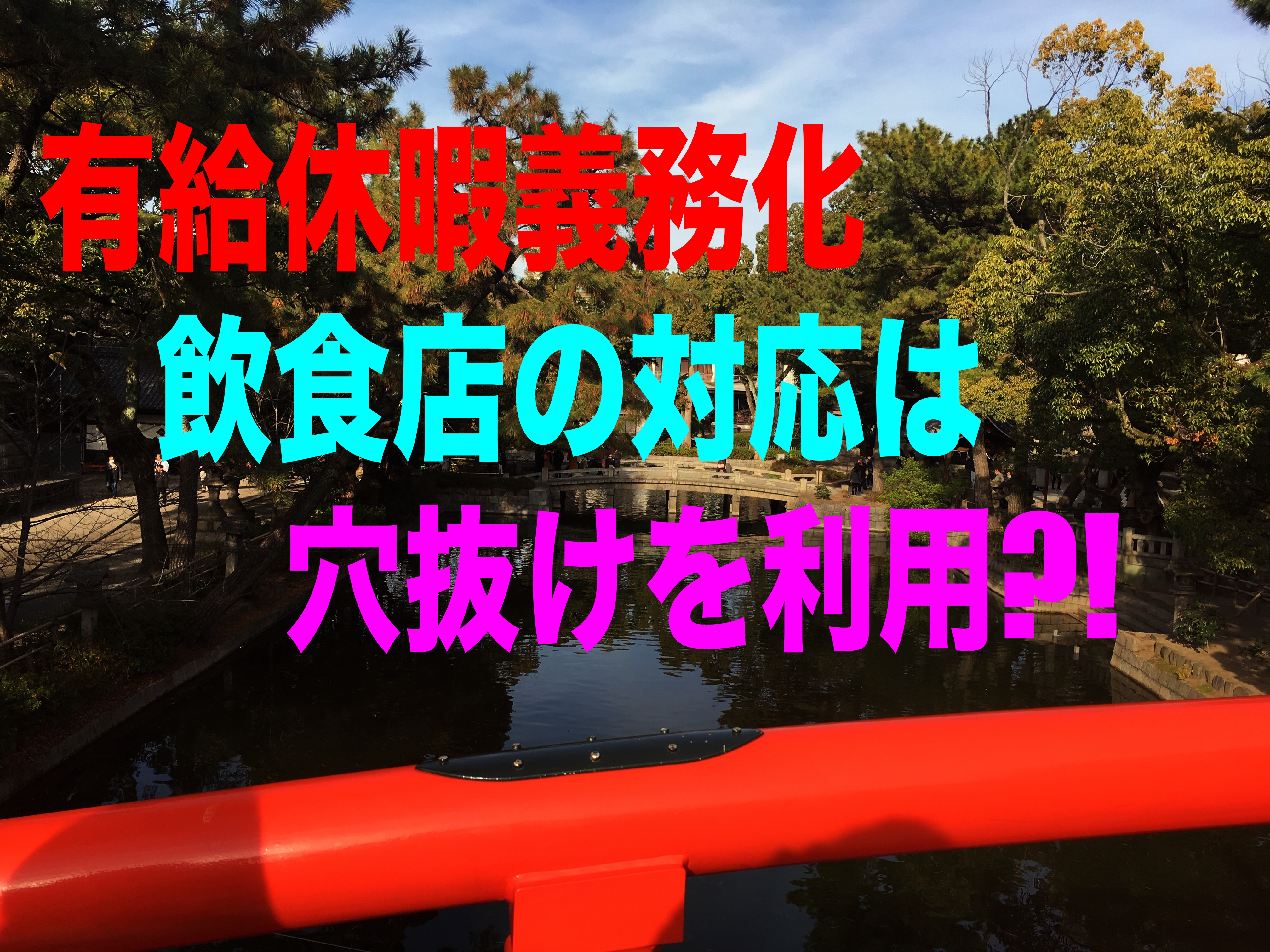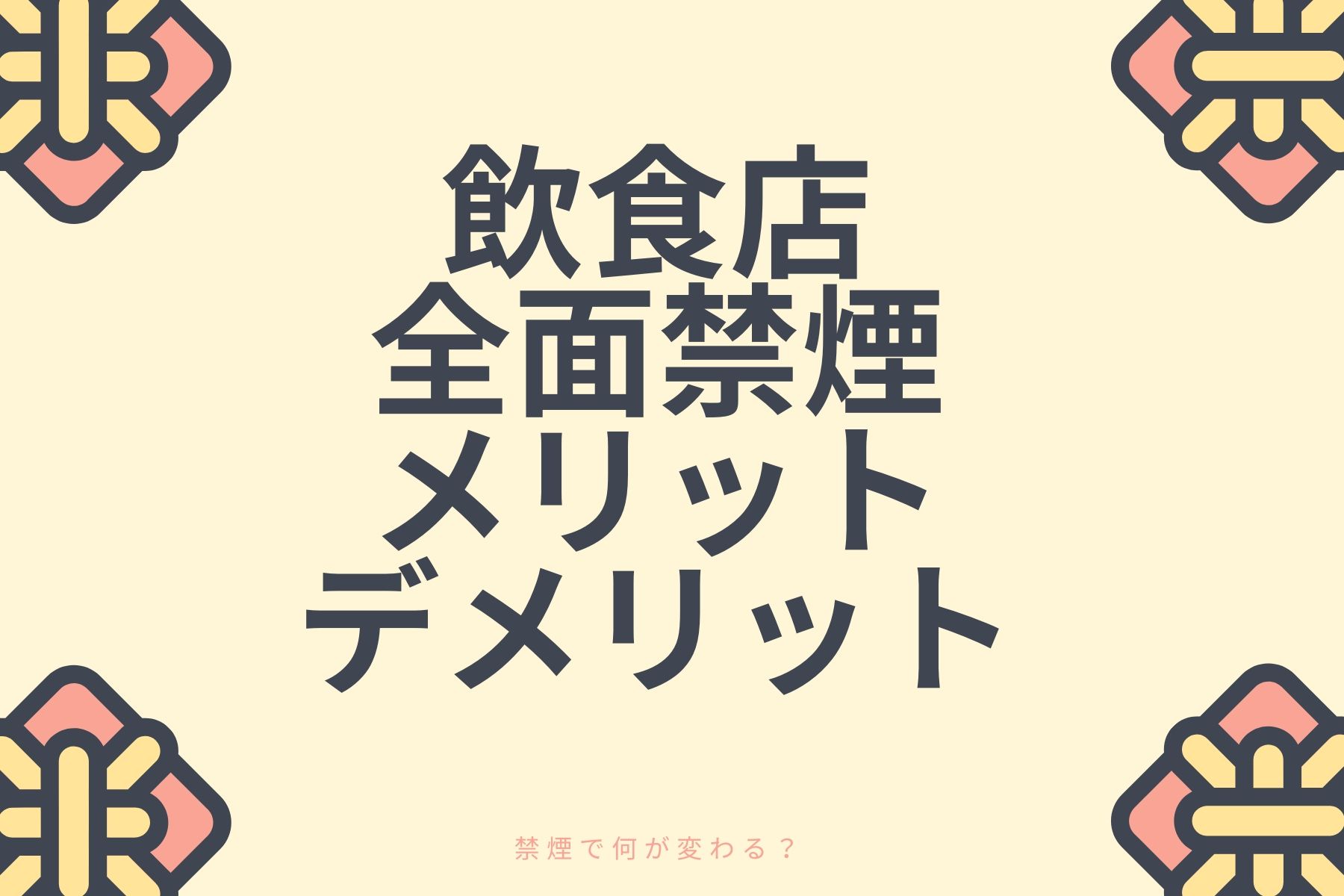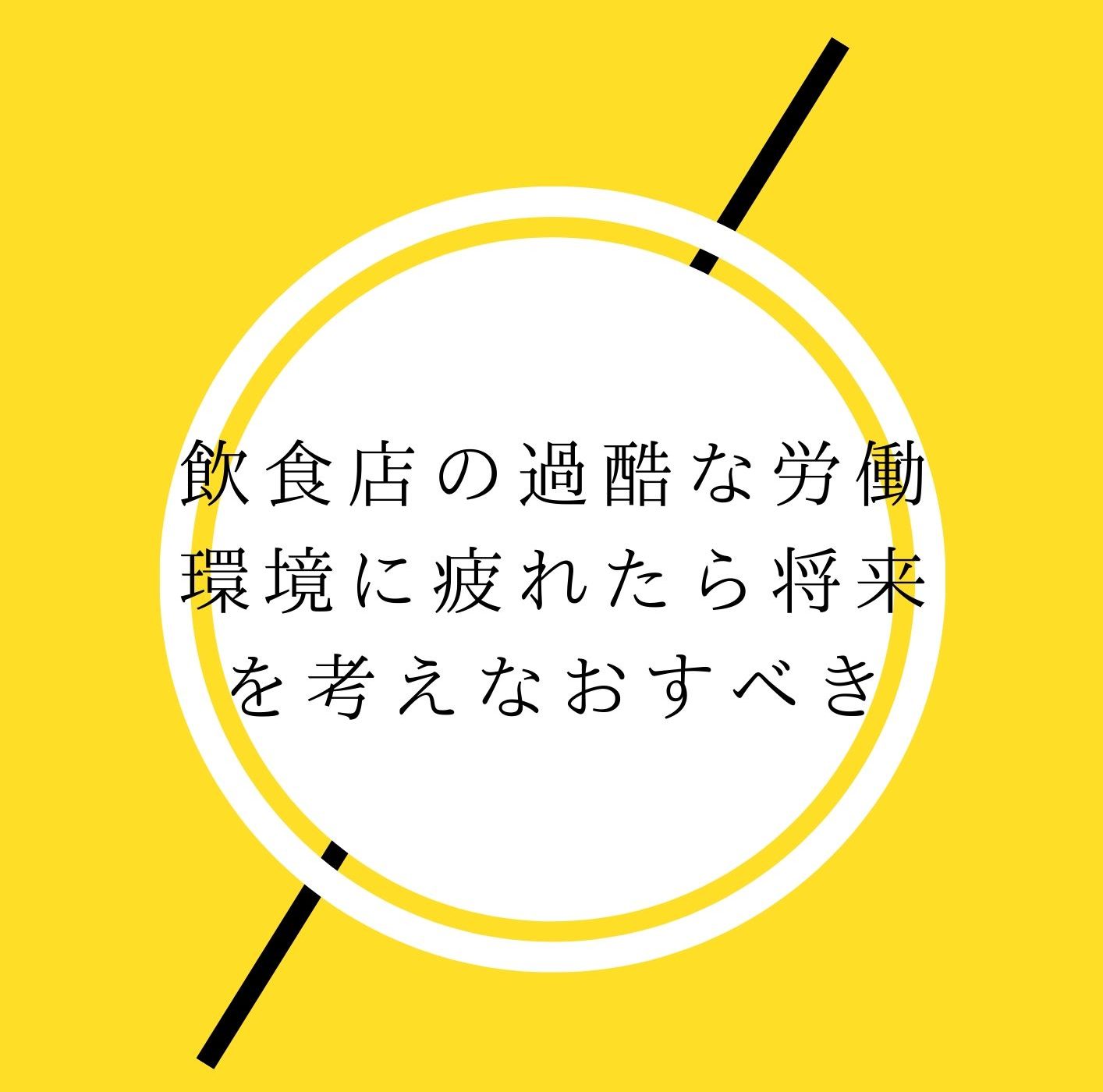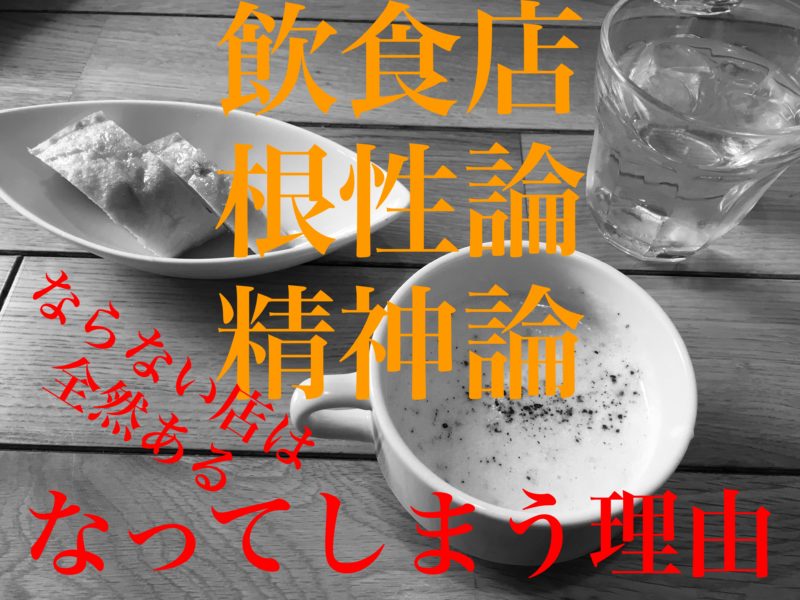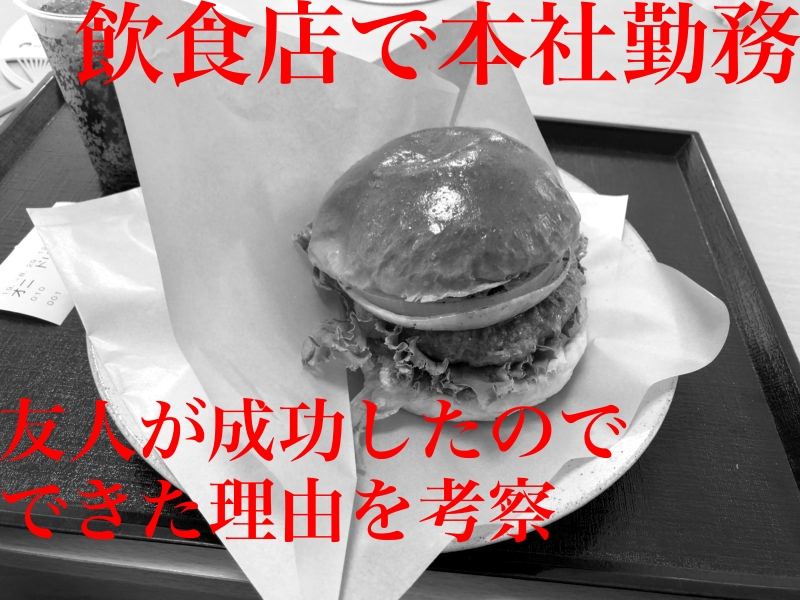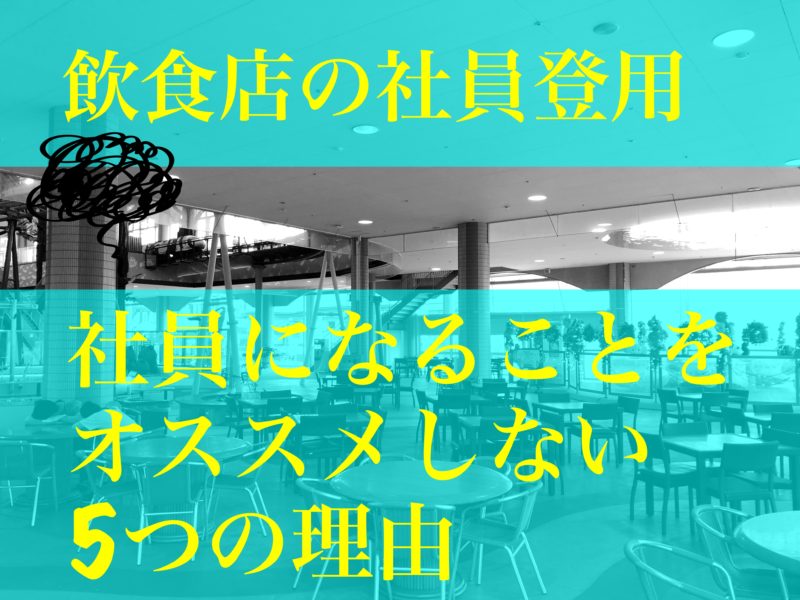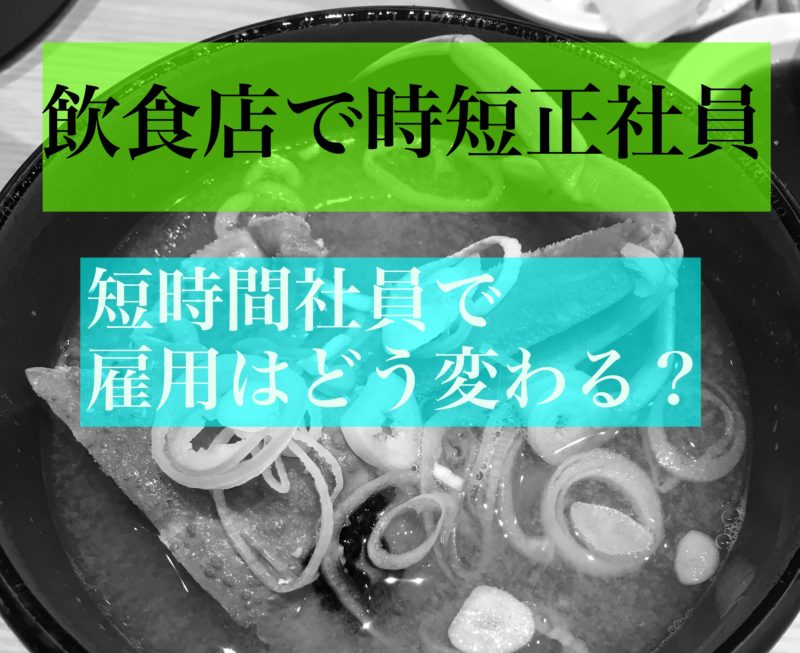2019年4月より年10日以上の有給休暇の権利がある従業員について有給休暇最低5日以上取得する事が義務化されます。
「日本人は働きすぎ」と言われているほど労働時間が長く、休めない会社員も多い中での有給休暇義務化は非常にありがたい話ですよね。
その一方で会社の9割以上がブラック企業と呼ばれる飲食業界、僕が8年働いていた飲食店でも有給休暇を取得する事はできず、取得するものなら
- 自分の事しか考えていないのか
- 店はどうなる
- 人が足らなくなる
と言われました。
休みが少なく多忙な飲食業界に置いて有給休暇義務化はどう対応していくのか?飲食店が仮に有給休暇義務化の為に有給休暇を消化させる為の抜け道を考えられる範囲でお伝えします。
有給休暇義務化における飲食業界の対応
毎月の休みが+1増える
飲食店の正社員の毎月の休みは平均すれば大体6-8日と思います。
僕が働いていた飲食店も奇数月=7日、偶数月=6日、といった週休2日(2日あるとは言ってない)方式を取っていました。
有給休暇義務化は年間で5日以上の取得を義務化です。とすると単純な話偶数月の2,4,6,8,10月の休日日数6日に+有給休暇として1日追加すればバランスを壊す事なく対応できます。
このポイントは繁忙期ではない部分で有給休暇を消化できる事です。例えば2.4.6.8.10月の中でも一番忙しくなるのが8月のお盆です。
しかしお盆と言えど店の対応としては「元々夏休みだしアルバイトも沢山入ってくれるので万事OK」な流れになっているので、お盆の期間さえ避ければ簡単に有給休暇を消化する事ができます。
上記の休みの方式以外にも大体の飲食店は繁忙期ではない月に有給休暇を消化させるようにするでしょう。
逆に言えばGWやお盆といった世間で言う長期休日期間や土日に有給休暇を消化させないと考えられます。(正社員が多ければ土日でも有給休暇を承諾できるでしょう。)
パート、アルバイトは排除される可能性
飲食店正社員の場合は休みが+1されるような感覚で有給休暇を取得させられると考えられるが、パート、アルバイトの場合は排除される可能性が非常に高い。
実際にパートアルバイトの有給休暇消化がなく罰則が出ないとわからないが、ちゃんとしている飲食店でも
「このパートさんのこの日の休みを有給休暇扱いにしよう」という使い方だと考えられます。
ようするにパートアルバイトが「この日有給休暇で消化してもいいですか?」という相談して消化するのではなく、シフトを組んでいる正社員が「この日有給休暇扱いでいい?」と相談して消化することになるでしょう。
飲食店におけるパート、アルバイトの扱いは有給休暇義務化でもまだまだ上がらないでしょう。また、これから飲食店でアルバイト、パートをはじめる人が
無知識、有給休暇義務化を知らない、取得できるかわからない
といった状況だと教えてもらえず、知らないフリをしてシフトを組むと考えられます。
有給休暇で就く労働時間は残業なし
元々残業がつかない飲食店は多いですが有給休暇でも残業はつかないでしょう。
僕が働いていた飲食店はなぜかシフト上に既に残業時間が設定されている謎な会社でしたが、有給休暇の場合8時間ほどしか労働時間がつかないと考えられます。
一つ注意点としては有給休暇は
- 実労働時間にはカウントされない
- 所定労働時間にはカウントされる
ことです。所定労働時間で評価している飲食店ならいいですが、実労働時間で評価している飲食店なら休みが1日増えるだけで実質他の日で余計に労働時間を増やさないといけない計算です。
飲食店なら有給休暇の扱いは残業代なしの8時間労働したことにするでしょう。どこの会社も一緒ですが注意点は抜け道になります。
有給休暇義務化における飲食業界の抜け道
会社規則、ルールでガチガチに固める
人手不足で悩む飲食業界に置いて有給休暇義務化と言うのは非常に邪魔な存在だと思います。
8年飲食店に働いてましたが、一度も有給休暇を消化することはありませんでした。
なぜなら会社規則、が存在し入社後3年働かないと有給休暇を取得できないルールになっていました。
3年も働いていれば有給休暇があることすら忘れてますし消化しようものなら「なぜみんなが働いているのにお前1人だけ楽しようとしているのか?」と詰められて取る事が出来ないからです。
これは有給休暇義務化が始まっても対応は変わらないでしょう。
例えば2年目の人は有給休暇義務化の存在を知っても有給休暇の消化するように相談をしても無理でしょう。
会社規則が元々あるのと人手不足の飲食店で有給休暇の話をしても煙たがられるだけです。
では有給休暇義務化で消化出来ない従業員の対応はどうなるか?簡単な話で年末に調整(休日の中から有給休暇を適用させる)されて、世間的には消化させているように仕向けると考えられます。
働いている本人は権限を言いにくいですし、会社側は働いている人に知らないで勝手に有給休暇を消化したように休日を5日削り消化している様に調整する、といった抜け道で対応する会社は出てくるでしょう。
今も今後も飲食業界の有給休暇は義務化しても変わらないと思います。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://business-ride.com/?p=2575]
パート、アルバイトでも同様に調整される可能性はある
パート、アルバイトも同様に調整されて有給休暇を消化していることにされる可能性があります。
もっとも、飲食店にありがちなパートさんが力を持っている店舗の場合を除き、パートが無知な人ばかりの店舗なら可能性があります。
力を持っている店舗ならまずパートさんが有給休暇の話をして消化することになりますが、年末調整を国が教えないのと一緒で得をすることを会社が言いません。
今後は働く上で有給休暇義務化は勉強しておきましょう。
実働労働時間で抜け道を作る
先ほどお話した通り、有給休暇は実働労働時間にカウントされず所定労働時間にのみカウントされます。
飲食店で所定労働時間で設定されていれば、残りの時間を有給休暇で調整すれば楽に働く事ができる流れになりますが、そうは問屋が卸さないでしょう。
有給休暇義務化から規約で実働労働時間で給料をつける会社も増加すると思います。そうなると有給休暇で休んでも毎月の必要な労働時間をクリアする事が出来ないので、結局1日当たりの実働労働時間が増えてしまうことになります。
法の抜け道であり人手不足の飲食業界では合理的な対応とも言えます。有給休暇義務化が始まったら契約書が変更されているかチェックは必要です。
月間休日から置き換え
一番考えられる対応かつ抜け道なのが月間休日から置き換えられることです。
飲食店のまともな企業なら月間休日+1有給休暇で対応すると思いますが、ブラック企業の場合既存にある月間休日の1日減らしその1日に有給休暇を取り入れると考えられます。
ほとんど休みのない飲食店で有給休暇は絶対邪魔に考える会社はあります。なら休日を一つ減らして1日消化させる様にすればいい、と考える会社も絶対あります。
事実休日出勤もある(僕は休み6日の中で3−4日出勤してた)ので、有給休暇に置き換えても従業員の気持ちとしては休日出勤にたまたま労働時間がついている、という感覚になると思います。
会社行事やイベントに有給休暇を使わせるケースも
例えば店長会議や会社セミナー、会社の行事を通常なら休日で消化していたところを有給休暇消化の日に合わせてしまう、というケースも増えるでしょう。
所定労働時間もつくので従業員も「労働時間がつくならいいか」と考える人も出てくると思いますし月間の休日を削られていない事に対して嬉しいと感じる人も出てくるでしょう。
僕が働いていた職場も毎月会社セミナーがありましたが、休日をそれで削られていたので有給休暇ならまだ良いか、と感じてしまうと思いますよ。
まとめ
有給休暇義務化における飲食店の対応と抜け道ですが、正直言って従業員の主張で有給休暇を取得できる様なものではない、と考えていた方がいいでしょう。
何かと会社の都合に合わせて有給休暇義務化分の5日を消化すると考えられるので、とりあえず今まで休日に当てられていた事が有給休暇によって消化される、と思う方が無難です。
優良企業なら従業員が欲しい時に有給休暇を消化させてくれると思いますが、人手不足が問題となる飲食業界は一握りくらいしかない
でしょう。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://business-ride.com/?p=2592]
上記の記事で紹介している会社の中なら有給休暇を消化している%も高く、それを見習って積極的に有給休暇を取得している飲食店も増加しているので、今働いている飲食店が「有給休暇義務化で何も変わってなくね?」と思ったら転職を考える時期かもしれませんよ。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://business-ride.com/?p=2894]